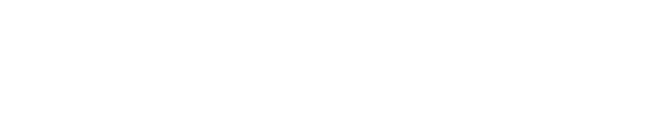パナソニック ホールディングス株式会社
|
POINT
|
|---|
坂田 幸太郎様
コーポレートR&D戦略室
エキスパート
博士(商学)
パナソニック ホールディングス株式会社は、物と心が豊かな理想の社会の実現に向けて、社会課題に向き合い、グループ全体としての新しい価値創造をリードしている企業様です。今回、2021年に調査プロジェクトを発注いただき、2023年からFusionをご導入いただいているコーポレートR&D戦略室 戦略企画部の坂田様にお話を伺いました。
ご利用の経緯について
世の中の技術の変化の兆しを早く捉える目的でVALUENEXのサービスを利用しています。
所属部門のミッションとご自身の業務について教えてください。
坂田様:パナソニック ホールディングス株式会社 技術部門 コーポレートR&D戦略室 戦略企画部に所属しています。ホールディングス技術部門はパナソニックグループ全体の研究開発の総本山のような位置づけにあり、物と心が共に豊かな理想の社会の実現に向けて、地球環境問題の解決、そしてお客様一人一人の生涯にわたる健康・安全・快適に貢献することを最重要課題としています。研究開発を推進する上では、この二つの課題解決に加えて、競争力の源泉となるようなコア技術群をグループ横断で特定し構築・強化を図っています。
ホールディングス技術部門は明日のパナソニックグループの事業を創造することをミッションとしています。ビジネス、テクノロジー、クリエイティブを融合しながら確実にくる未来が求める価値を生み出しながら、理想的な暮らしや社会を実現して社会課題をグローバルに解決することを目指しています。
持続可能な地球環境とより良いくらしの両立の実現に向けて、私の所属するコーポレートR&D戦略室は世の中の価値変化を先読みして技術ポートフォリオを組み換え、事業創出の仕掛けを構築することで当社の事業競争力を維持強化することがミッションになります。
コーポレートR&D戦略室の取り組みは大きく分けて4つあります。1つ目は、技術の変化の兆しをもとに社会・お客様が我々に求める価値変化を見極めること。2つ目は、価値変化に合わせて技術ポートフォリオを最適化することでグループ全体の将来的な成長を促進すること。3つ目は、技術ポートフォリオに基づく技術強化政策で事業創出や改革を確保すること。最後に、共通技術基盤の整備活用によってグループ全体の事業競争力を強化する、グループ全体の技術行政の役割を担っています。
特に1つ目の事業、政策、技術の変化の兆しの抽出という取り組みの中で、技術の変化の兆しを早く捉える目的でVALUENEXのサービスを利用しています。
変化の兆しを捉える取り組みとはどのようなものでしょうか?
坂田様:当社には様々な事業ドメインがありますが、5年後、10年後に技術的なブレイクスルーが見込まれていて手を打つべき、あるいは現状当社で手を打っていないが世の中の価値変化や動向を見たときに手を打つべきという技術領域がいくつかあると考えています。
そのような技術領域について、様々な情報ソースから数百の技術テーマを抽出して、さらに社会のインパクトの観点で優先順位付けして絞り込み、ショートリストとしてウォッチすべき技術テーマを定めています。世の中や自社の動きに合わせて優先度は変わってくるので、その時々で優先度の高いテーマについて調査しています。例えば、「生成AI」などが該当します。
このようにして選定した技術テーマについて、VALUENEXのサービスを用いて調査分析を行っています。
VALUENEXのサービスをご利用される前はどのような課題感をお持ちでしたか。VALUENEXを選んでいただいた理由についても教えてください。
坂田様:私が2020年にコーポレートR&D戦略室(当時のイノベーション戦略室)に異動した初年度に、新たな骨太の技術開発テーマを検討するプロジェクトが立ち上がりました。そこでは、今日のイノベーションを牽引するスタートアップの動きを捉えることが大事と考え、例えば、XR(※1)など、いくつかの注目される技術テーマに関連するスタートアップの動向を捉えようとしていました。しかし、実際にXRのスタートアップを調べるとグローバルで数千社が該当します。このような膨大な数のスタートアップの動向をどのような方法で捉えればよいかという課題を当時抱えていました。人力で1社1社見ていくにも限界がありますので、何かしら自動的に分析できる切り口がないか検討する中で、VALUENEXのツールに辿り着きました。
VALUENEXコンサルタント(林尚芳):実は当時、VALUENEXでは特許や論文の分析がメインで、スタートアップ分析の事例はあまりありませんでした。そこで、「こういう観点でこう分析すれば、こういう知見が得られるのではないか?」と坂田様と密に提案・議論させていただき、一緒に分析手法を構築していきました。
坂田様:VALUENEXの俯瞰図作成の手法を用いれば、スタートアップの取り組みのテキストデータから俯瞰図を作成して分析に転用できるのではないかと着想し、相談しました。
スタートアップ分析はどのような手法で行ったのですか?
坂田様:本来はスタートアップの技術動向を見たかったのですが、スタートアップのデータベースは事業内容の情報がメインなので、直接、技術内容を見るのは難しいです。そこで、スタートアップは市場の動向を捉えるための情報として分析しました。俯瞰図を作成した後は、注目すべきクラスターを特定し、調査対象を数十社に絞って技術に注目しました。つまり、スタートアップの優劣を分析してから注目技術を特定する二段階の分析です
スタートアップにはライフサイクルがあり、VC(※2)の投資家の注目領域もどんどん移り変わっていくと考えています。有望なクラスターを評価する方法としてVC投資の増減の傾向などの指標を開発して、注目領域を特定する手法を作り上げていきました。
スタートアップ分析の後に、論文・特許・スタートアップ情報を用いたFusionによる分析調査プロジェクトを実施しましたが、どのような経緯で進んだのでしょうか?
坂田様:こちらも私から相談しました。2021年にスタートアップ分析の結果が出て、VALUENEXのツールを使った分析のアウトプットが社内でも理解されはじめました。その後、基礎研究や技術開発の動きを捉えるために論文や特許の動きも見たいと考えました。スタートアップではなかなか技術の動向に迫りきれないところもありますが、論文と特許の情報を融合することで技術分析の質が向上すると考えました。プロジェクトが特許だけや論文だけの分析にならなかった理由は、技術の変化を追いたいというニーズや、スタートアップの動きを捉えたいというニーズがあったためです。
実際に分析したところ、論文や特許はスタートアップよりも前段階で動きが出ていて、その後にその技術を基にしたスタートアップに盛り上がりが出ていたので、リーズナブルな結果が得られました。
当社とのプロジェクトの後にFusionの分析コーチングサービス(※3)を利用いただきました。
坂田様:コーチングサービスは、分析のアウトプットを自前で作れるようになりたいということで利用しました。アフターフォローも含めて5か月間と丁寧に時間をかけていただきました。最初の頃はコーチングを受けていた者も「これは何をやっているんだ?」という感じで苦戦していましたが、最後にはかなり習得できました。今では毎回どんな結果になるかワクワクしながら分析に取り組めていると思います。
林尚芳:5か月もの期間になったのはテーマが2個あったためという背景があります。テーマは簡単なお題ではなく、坂田様に提供いただいた実践的なテーマで実施しました。さらに、情報ソースも特許、論文、スタートアップと3つあったので、みっちりとノウハウ提供させていただきました。
坂田様: 結果オーライかもしれませんが、簡単なお題ではなく実践的なテーマでボリュームがあるものを扱ったことで、その後自走しやすかったと感じます。
Fusionを導入されてから成果物をどう活用していますか?
坂田様:我々のミッションである、世の中の技術進化・価値変化を見極めるインテリジェンス活動に活用しています。ホールディングス技術部門では、当社が目指す2040年の社会を「技術未来ビジョン」として策定していて、2024年7月にグループCTOの小川より発表しました。コーポレートR&D戦略室では、発表後もビジョンを磨き続けるべく、世の中の技術の進化やその兆しを捉えることを継続しています。重要な技術テーマについては分析レポートとしてまとめているのですが、このレポートにFusionを利用したスタートアップ・VC投資動向の分析を掲載しています。
レポートに掲載された俯瞰図を見た方からのフィードバックを教えてください。
坂田様:レポートを見る方は技術者が多いので、レポートの分野の専門家が見たときにも「やっぱりそうですよね」というリアクションをされることがあります。一方で、俯瞰図の軸の意味について聞かれることもあり、俯瞰図の読み方についてはコミュニケーションが必要だと感じています。一方、マネジメント層からは俯瞰図から得られるインサイトに注目されます。
VALUENEXへの要望や期待することを教えてください。
坂田様:Fusionのアルゴリズムについては、定点観測ができるようになってほしいです。生成AIの技術などは動きが速いので数か月といった単位で定点観測したいのですが、現状では注目すべき新しいトピックやクラスターは自動では検出されないため、手作業で追加して再分析することが必要です。トピックやクラスターが自動で追加されるとありがたいですね。
今後もVALUENEXのコンサルティングサービスを利用いただく際には、どのように活用されるでしょうか?
坂田様:論文、特許、スタートアップ以外に新たなデータソースを分析する際などにはご相談したいと思います。
分析のアルゴリズムの観点でも、今のツールではできない新たな分析の切り口や指標が必要になった際にご相談したいと思います。
注釈
※1 XR…クロスリアリティ。現実世界とデジタルな仮想世界を融合させるAR、VR、MRなどの技術の総称 。
※2 VC…ベンチャーキャピタル。未上場の新興企業(スタートアップ企業)に出資する会社のこと。
※3 VALUENEXのコーチングサービス…VALUENEXのコンサルタントに分析に必要なテクニックの手ほどきを受けるサービスのこと。